
コラム
犬や猫の「肛門腺絞り」は本当に必要?|その理由と注意点【獣医師が解説】
「最近、うちの子がよくお尻を床にこすりつけている」「肛門のあたりをしきりに舐めていて、なんだかにおいも気になる」
もしかすると肛門腺のトラブルが原因かもしれません。
そのまま放置すると炎症を起こすだけでなく、細菌感染によって「膿瘍(のうよう)」と呼ばれる膿の溜まった腫れに進行することもあるため注意が必要です。
今回は、肛門腺の意外な役割や肛門腺絞りが必要になるタイミング、そして見逃してはいけない注意サインについて解説します。
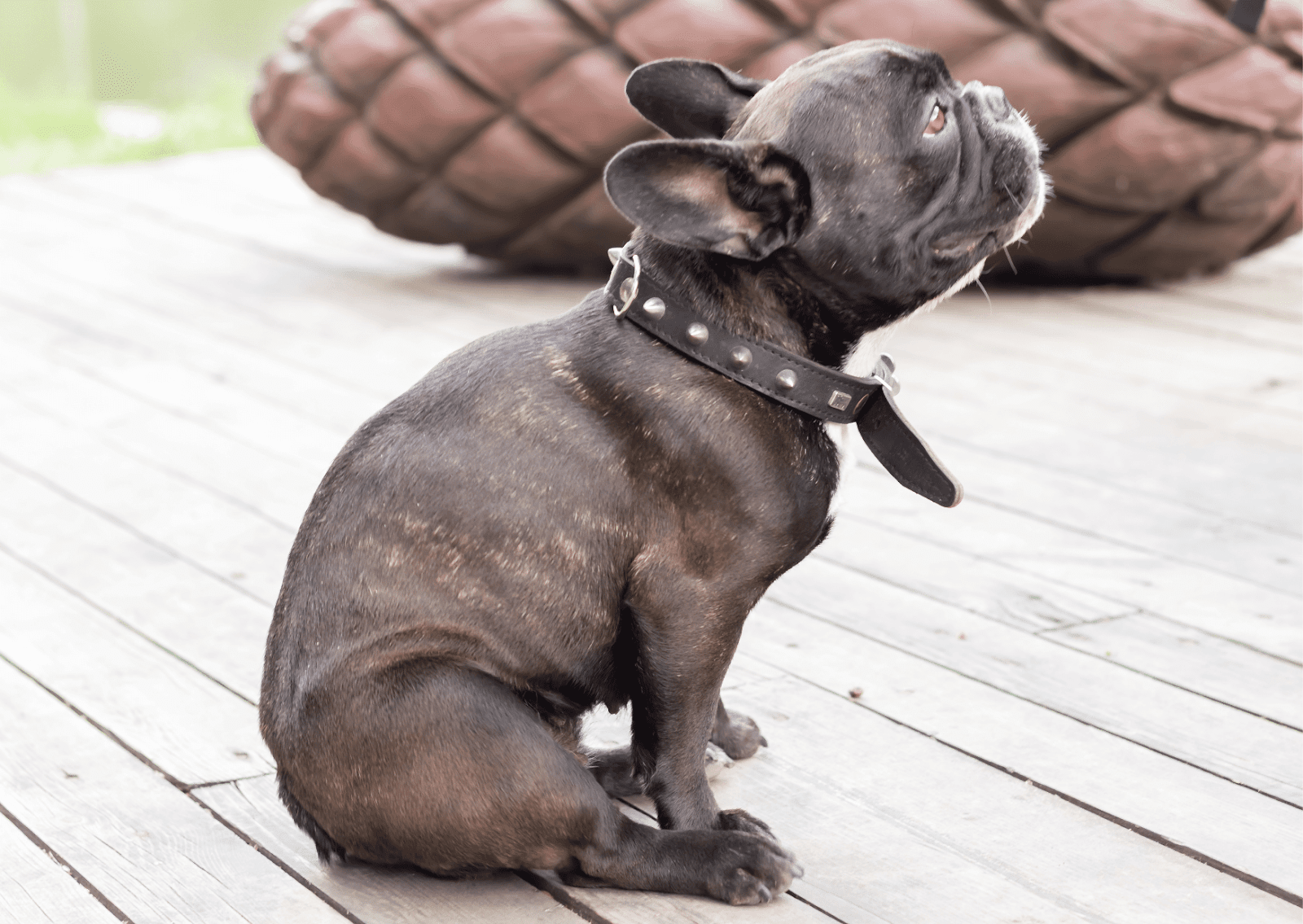
肛門腺とは?|その働きと気をつけたいトラブル
犬や猫の「肛門腺(こうもんせん)」とは、お尻の左右(時計の文字盤でいうと4時と8時の位置)にある分泌腺のことを指します。
肛門のすぐ内側には、「肛門嚢(こうもんのう)」という小さな袋状の器官があり、そこに強いにおいを持つ分泌液が溜まります。
この分泌液には、それぞれの動物が持つ特有のにおいが含まれており、もともとは縄張りを主張したり、自分の存在を他の動物に知らせたりするための大切な「においのサイン」として使われてきました。
注意したい肛門腺のトラブル
現代の家庭で暮らす犬や猫たちは、自然界に比べて運動量が少なかったり、排便の刺激が十分でなかったりすることで、分泌液がうまく排出されなくなることがあります。
すると、肛門腺の中に液がどんどん溜まり、以下のようなトラブルにつながります。
・肛門腺うっ滞(分泌液が溜まって詰まりやすくなる状態)
・肛門腺炎(溜まった液に細菌が入り、炎症を起こす)
・肛門腺膿瘍(のうよう)(腫れて膿が溜まり、破裂することもある)
このような状態になるとお尻に強い違和感や痛みを感じ、排便を嫌がったり、元気がなくなったり、食欲が落ちてしまうこともあります。
ただし、肛門腺のトラブルはすべての犬や猫に起こるわけではありません。まったく問題なく過ごせる場合もあれば、何度も肛門腺が詰まりやすい体質の犬や猫もいます。
とくに注意が必要なのは、小型犬(チワワ、トイプードル、パピヨンなど)や、肥満傾向のある犬猫、高齢の犬や猫です。
こうした傾向が見られる場合は、日頃からお尻の様子や排便後のしぐさをよく観察し、少しでも異変を感じたら、早めに対処してあげましょう。
肛門腺絞りは必要?|タイミングと気をつけたいサイン
すべての犬や猫に「肛門腺絞り」が必要かというと、必ずしもそうではありません。
排便の際にしっかりと肛門腺液が自然に排出できている場合は、無理に絞る必要はありませんし、過剰な肛門腺絞りはかえって皮膚に炎症を起こしてしまうこともあります。
肛門腺絞りが必要かどうかを判断するためには、以下のような行動やサインをチェックしてみてください。
・お尻を床にこすりつける
・肛門のあたりをしきりに舐めたり、噛んだりする
・お尻が気になる様子で、落ち着かない
・肛門の周囲から独特なにおいがする
・座るときに違和感を示す(斜めに座る、頻繁に立ち上がる など)
こうした様子が頻繁に見られる場合は、肛門腺液が溜まっている可能性がありますので、早めに動物病院に相談しましょう。
動物病院での肛門腺ケア
ご自宅で肛門腺絞りに挑戦される飼い主様もいらっしゃいますが、力加減や方向を誤ると肛門腺を傷つけることや、炎症を引き起こす原因になることがあります。初めての場合や不安がある場合は、動物病院で処置してもらうのが安心です。
また、トリミングの際に肛門腺絞りもお願いしているという飼い主様も多いかもしれません。日常のケアとしてトリマーに任せる方法もありますが、腫れやしこりなどの異常が見られる場合には獣医師による診察が必要です。
動物病院での肛門腺処置では、単に分泌液を出すだけでなく、腫れや痛み、しこり、出血の有無などを獣医師が丁寧に確認します。
とくに、肛門腺の中にしこりが見つかった場合、腫瘍(肛門周囲腺腫や肛門嚢アポクリン腺癌など)が隠れている可能性もあるため、視診と触診での見極めがとても重要です。
さらに、肛門腺の出口が詰まっている場合や感染を起こしている場合は、通常の方法では膿が排出されないこともあります。そのようなときは、抗生剤による治療や、膿瘍の切開・洗浄といった処置が必要になるケースもあります。
このように、肛門腺のトラブルを繰り返す体質の犬や猫や、肛門腺絞りをしてもすぐに再び溜まってしまうような場合には、月に1回程度の定期通院をおすすめしています。
ご家庭での肛門腺ケアに不安がある場合は、いつでも当院へご相談ください。
肛門腺トラブルを防ぐために|毎日のケアでできること
肛門腺の健康を保つには、日常生活の中でのちょっとした心がけが大切です。
まず注目したいのは「便の質」。
適度に硬さのある便は排便時に肛門腺の出口を自然に刺激し、中に溜まった分泌液を押し出す助けになります。そのため、食物繊維を適度に含んだバランスの良い食事は、肛門腺の自然な排出を促すうえでとても効果的です。
また、日頃の運動も欠かせません。
肥満は肛門腺トラブルの大きな原因のひとつです。運動不足になると便が柔らかくなりやすく、排泄力も落ちてしまうため、適度な運動で体重を管理することが大切です。
さらに、定期的な獣医師によるチェックも予防には欠かせません。
見た目ではわからない炎症や腫れが進行していることもあるため、ワクチン接種や健康診断の際に、肛門腺の状態も一緒に確認してもらうと安心です。
ご家庭でのケアと動物病院でのチェックをうまく組み合わせて、愛犬・愛猫の肛門腺トラブルをしっかり予防していきましょう。
まとめ
肛門腺は、普段あまり意識することのない小さな器官かもしれませんが、犬や猫の健康と快適な暮らしにとって実はとても大切な部分です。
分泌液が溜まりすぎると不快感や痛みだけでなく、炎症や感染などのトラブルにつながることもありますが、適切なタイミングでのケアや食事・運動といった日常の心がけによって、トラブルは予防することができます。
当院では、肛門腺に関するご相談にも対応しており、それぞれの体質や暮らしに合わせたケアをご案内しています。
「少し気になるかも」と感じた際には、お気軽にご相談ください。
千葉県市原市の動物病院なら「姉ヶ崎どうぶつ病院」
